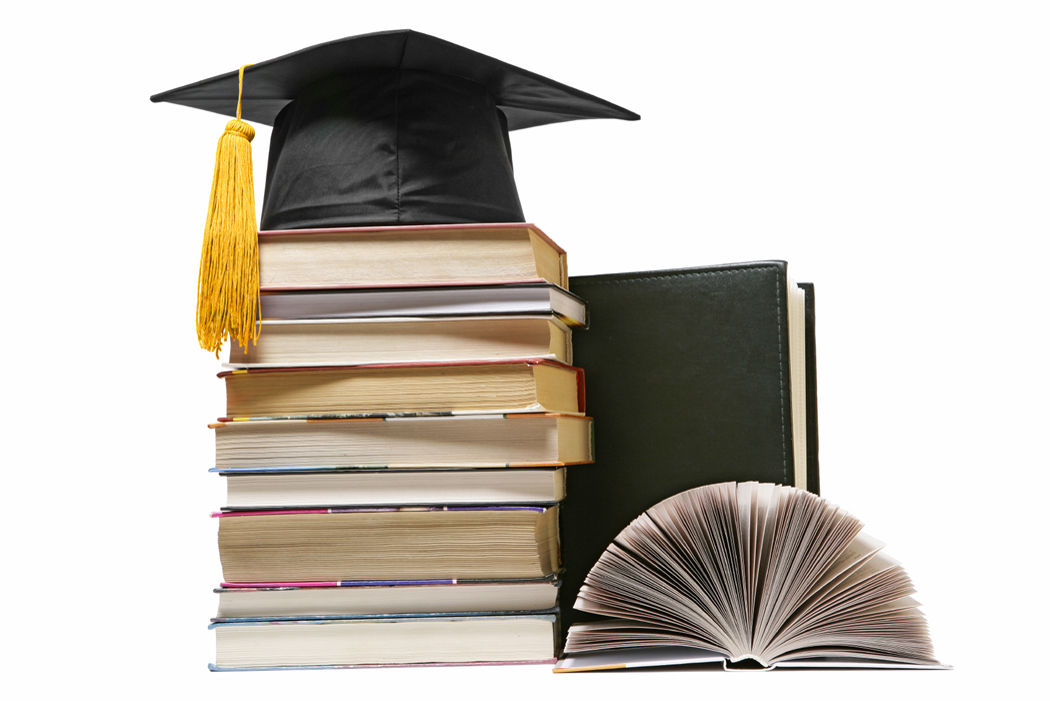
私も今から30年以上前に日本の国立大学の理系学部に在籍していた時に、アメリカの州立大学に短期の語学留学をしたことがあります。また、私の娘も大学そして大学院と教育のすべてはアメリカで終えました。それらの身近な経験の中からいえることは、少なくともアメリカの大学では日本のような理系とか文系とかいった専攻する分野の明確な仕分けや制限を設けていないということでした。日本の大学にいる限りにおいては、私の在籍していた30年前も今もほとんど大差はないのではないかと思いますが、例えば理学部に在籍しながら、同時に文学部にも在籍でき、両方の学部からの学位を取って卒業するということは、自分のクローンでも作る以外には不可能なことではないかといえます。ところがアメリカの大学では、このようなことは十分可能で、ダブルメイジャーとして、異なった学位をもって卒業する学生はそこそこいるのが現実なのです。
アメリカの大学のUndergraduate と通常呼ばれている4年間は、もちろん選考学科(Major)を決めて勉学に励むわけですが、何もひとつのMajorだけに固守しなければならない規制もプレッシャーもなく、2つのMajor(この場合をDoubleMajorと呼ぶ)にしてもよいし、Minorといって副専攻学科をMajorのほかに選択してもよいといった柔軟性に富んでいるのが大きな特徴となっています。このような柔軟性は日本の大学ではほとんど聞いたことがないのですが、実際はどうなっているのでしょうか。日本を離れ、しかも日本の大学との距離が甚だしく開いてしまっている現在の自分には、理解していない部分も多いとは思いますが、やはり今も昔も大きな差はないように感じます。
アップルのスティーブ・ジョブズがiPadの発表会で、「テクノロジーとリベラルアーツの交わる場所」と語ったのは、新製品開発での成功を如実に現しているように感じます。かつてのソニーにも似たようなところがあったのではないかと思えますが、いまやそれも遠い昔の話です。だいたい、複雑化するばかりのこの世の中にあって、単純にこれは理科系の問題、これは文科系の問題などといって割り切れるような時勢ではないわけです。日本では、例えば複雑な量子力学の話などがどこからか出てきたら、「私は文科系出身だから」などといって、理解しようとすることの拒絶を十分に正当化できてしまいます。同じく、小説などの文学作品にまったく疎い人は、「理科系なもので、文学はどうもね」といって、やはり自分の教養のないことを周りにいともたやすく納得させてしまうことが出来ます。
アメリカの大学を出た人の中には、Majorは、コンピューターサイエンスで、Double MajorやMinorは、アメリカ近代文学やヨーロッパ中世史だったりといった人が少なからずいるものです。そうすると、もはやその人を理科系・文科系と区別することが出来なくなりますし、意味のない不毛な仕分けであるということにもなります。娘が卒業した大学は、ワシントン州タコマにあるUniversity of Puget Sound (通称UPS)というリベラルアーツ系としては有名な私立大学でした。大学の入学式での祝辞スピーチで、UPSの大学総長は、さかんに “Inter-discipline” という言葉をちりばめてして話をしていました。
日本語に訳すとInter-disciplineというのは、「学際的」と呼ばれるようですが、総長が言いたかったのは、学問を理系や文系に仕分けして私は理系志望だから文系のことは関心もなく、だから勉強しなくてもよいといったような態度を戒め、新しい学問の領域とは、それこそスティーブ・ジョブズが言うように、理系と文系の交わるような場所にあるのだと振り返っててみれば、そのような意味を込めて話をしていたような気がします。
日本では、若い世代の理系離れが深刻だという話が聞こえてきてから久しいのですが、アメリカではそれはあまり耳にしません。そもそも日本のような理系・文系の分け方がなされていないので、そのような話が出てこないのではないかと思われます。日本の大学もアメリカの大学のように、理系・文系に関らず、もっと自由に自分の専攻する分野を選ぶことが出来るようになることが、理系離れという現象を回避するひとつの特効薬になるのではないかという気がいたします。
まあそんなことをいっても、100年以上続けている日本の大学制度を根本的に変えることなど机上の空論だと一括されてしまうのがせいぜいのところなのでしょう。ということで、日本では残念ながら、アップルを凌駕するような新製品の開発は、あと何十年経ってもそう簡単には出てこないであろうといわれても反論できる余地はほとんどありません。諦めてiPodの二番煎じの擬似製品を作るしか手がないのでしょうかね。ますますアップルの快進撃はこれからも当分続くことになり、彼らの独壇場を傍らから固唾を呑んで静観しているしかないとしたら、ちょっと悲しすぎませんか。
P.S.パシフィック・ドリームス社のサイトにも是非お立ち寄りくださいね。サイトは毎日更新しています。http://www.pacificdreams.orgまで。

コメント